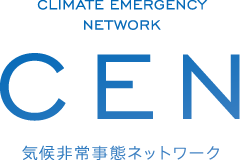海洋研究開発機構(JAMSTEC)が2026年1月に南鳥島の沖合でレアアースの試掘掘削を始めます。海底6,000mに溜まっているレアアース泥を海上まで汲み上げる「サブシープロダクションシステム」という解泥・揚泥機を使って行います。泥を解きほぐして集め、それを船まで引き揚げる。簡単そうに聞こえますが、6,000mもの深海から資源を引き揚げるこのようなシステムは世界初の技術だそうです。
こちらのサイトにあるイラストを見ると、どんな技術なのかイメージが掴めます。
ところで、そもそもこの南鳥島沖のレアアースはどのようにしてできたのか。ぼーっとレアアースの記事をあれこれ見ていたら、偶然見つけてしまいました。5年前に発表された東京大学の加藤泰浩教授らの研究成果によると、約3,450万年前の地球の寒冷化が大きく関わっていたようです。「え、なんで寒冷化が関係あるの?」と思ったのですが、読んで納得です。
南鳥島沖の「超高濃度レアアース泥」は地球寒冷化で生まれた(早稲田大学、2020年6月19日)
この時期、地球規模の寒冷化によって氷床が出現。すると冷えて重たくなった海水が沈み込むことで底層流が強くなり、それが大きな海山に衝突して湧昇流が発生し、海洋深層に含まれていた大量の栄養塩が海洋表層に運ばれます。そのおかげで魚などの海洋生物が増加します。
その魚たちが死んで、骨が海底に堆積すると、なんとその骨が海水中からレアアースを高濃度になるまで凝集したのだそうです。なので、南鳥島沖のレアアース泥には魚の骨が大量に含まれています。
魚の骨が時間をかけて集めてくれたレアアース。なんだか、手を合わせて「いただきます」と言いたくなる感じです。
海底の泥の採掘なので、もちろん環境への悪影響が懸念されます。しかしその一方で、この記事にある「だとすると、こんな海域に超高濃度レアアースがあるんじゃないか?」という地図を見ると、ついワクワクもしてしまいます。資源開発と環境保護。両立していきたいものですね。
さて、東京大学の主催で「気候変動下の国土」について考えるシンポジウムが開催
されるのでご案内します。
名称: 共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)拠点連携シンポジウム2025
~気候変動下の国土について考える~
日時: 2025年7月11日(金)13:00~17:00
会場: 東京大学/オンライン
主催: 熊本県立大学 地域共創拠点運営機構
「流域治水を核とした復興を起点とする持続社会」地域共創拠点
参加費: 無料
主な内容:下記HPより抜粋
講演1「共創の流域治水とは」
講演2「流域治水と多自然川づくり-水をゆっくり流す技術と実践-」
講演3「流域治水を見える化する-水文・水理モデルでできること-」
講演4「IoT技術の小集落での展開」
講演5「杉並区役所 グリーンインフラの取り組み」
講演6「ClimCOREプロジェクトの目指すもの」
講演7「熊本県におけるキキクルとClimCOREの地域気象データを活用した豪雨対応訓練と展開」
講演8「持続可能な保険制度とグリーンレジリエンス」
パネルディスカッション
詳しくはこちらをご覧ください。