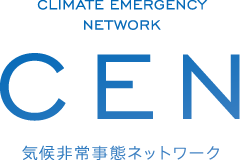少し前に見た1980年代のフィンランド映画のラストシーンで、二人の男女が首都ヘルシンキから逃避行する場面がありました。赤い鎌と槌が描かれたフェリーに乗って、フィンランド湾の向こう側にあるエストニアの首都タリン(当時はまだソ連支配下)に向けて旅立って行く姿を見て、おー、ロマンチックだなぁと思うのと同時に、この地域の人たちにとっては外国って結構身近なものなんだろうな、とも思いました。
フィンランド湾はバルト海の一部。バルト海沿岸には西側から時計回りにスウェーデン、フィンランド、ロシア、エストニア、ラトビア、リトアニア、ポーランド、ドイツ、デンマークがあり、ぐるりと囲んでいます。ちょっと船の向きを変えるだけでいろんな国に行けてしまう海なんですね。バルト海を周遊するクルーズ船内は免税店が充実していて、化粧品や衣類、お酒などが安く買えて人気なのだそうです。
地図を見るとよく分かるんですが、狭い海峡で北海と繋がっているだけなので、閉鎖性の強い海域になっています。水が滞留しがちであるため、1970年代から90年代にかけてはかなり環境汚染が進んでしまったそうです。
やがて各国の環境汚染対策が進む中、2005年に国際海事機関(IMO)がバルト海を「特別敏感海域」(Particularly Sensitive Sea Areas, PSSA)に指定しました。海洋保護区の一種です。生態学的、社会経済的、科学的に重要で、しかも国際海運活動による損害に脆弱で、IMOによる保護を必要とする海域のことです。国際的な「航行の自由」を保ちながらも海洋環境の保護を目指すためのもので、現在までにグレートバリアリーフやガラパゴス諸島など19海域が指定されています。
このバルト海の環境保護に2016年以来取り組んできたのがポーランドのMARE財団(Mare Foundation)で、様々な活動を行っていますが、そのうちの一つがオペレーション・ゴースト。
海中に遺棄された漁具”ゴーストネット”が亡霊の如く海を彷徨い、海を汚すだけでなく、海洋生物をとらえてしまう状況が起きています。欧州委員会の調べでは、海中ゴミの49%がシングルユースのプラスチックで、27%が遺棄された漁具です。オペレーション・ゴーストでは、沈没船に絡みついた漁具を潜水夫が潜って取り外し大型船を使って回収する、という気が遠くなるような活動を行っています。下記の財団のサイトで作業の様子を見ることができます。
MARE Foundation: Operation Ghost(英語字幕に設定できます)
いやあ、これは大変な作業です。終わりは見えないのだと思いますが、それでも、こうした活動があるからこそこんな問題があるんだということが広く知られて、少しずつ人々の意識を変えて行くんですね。
さて、大阪万博では、会場でもオンラインでも参加できる様々なイベントがあります。そのうちの一つで「国際海洋エコロジー会議 – ポーランドの海の日」というものが開催されるのでご案内します。MARE財団の活動についても話が聞けます。
名称: 国際海洋エコロジー会議 – ポーランドの海の日
日時: 2025年7月21日(月)10:00~12:30
会場: 大阪万博テーマウィークスタジオ/オンライン
主催: 公益社団法人 2025年日本国際博覧会協会
参加費: 無料
主な内容:下記HPより抜粋
本会議では、ポーランドの地方自治体と日本・ポーランドの科学界・ビジネス界の共催で開催されます。その一環として、グディニャ海洋大学と東京海洋大学が海のエコロジーに関する研究成果を発表します。ポーランドのENAMOR社をはじめとするポーランドと日本のパートナーが、海底調査におけるソリューションを紹介します。
また、プログラムの一部として、ポーランドのMARE財団は、バルト海から海洋ごみ、特に逸失された漁具(いわゆる「ゴーストギア」)を回収する、定期的に行われる「クリーン・バルト海」キャンペーンを紹介し、回収されたごみの再利用方法について説明します。
本会議に合わせて、ポーランドパビリオンとしては他の参加者のパビリオン・チームも誘い、沖ノ島の水辺清掃キャンペーンを実施します。そして、本会議のフィナーレを飾るイブニングコンサートでは、シュチェチン海洋大学合唱団が海の名曲を万博会場内のステージで披露します。
詳しくはこちらをご覧ください。