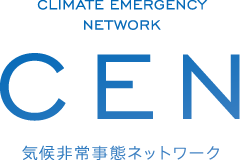「ウナギは陸でも狩りをする」
この記事の見出しを見たとき、持っていたコーヒーカップを危うく落としそうになりました。東京大学と国立環境研究所の研究グループの成果ですが、水中からわざわざ陸に這い出てきてバクリッとカニやコオロギ、ゴキブリ、ムカデなどを食べていることが分かったそうです。
ウナギは陸でも狩りをする -魚類の陸上進出に関する新たな発見-
(2025年10月17日 東京大学)
この記事に、オオウナギがカニを咥えている写真が掲載されています。さすがウナギだ。小学生の頃に近所の農業用水路でウナギを釣り上げたことがあるのですが、そのときのウナギのぐいぐい引っ張る力強さが強烈な記憶として残っています。「環境が変わるから生きづらいって?水中で食えなきゃ陸に上がるだけよ。しっかり見とけ」という声が聞こえてきそうです。やっぱりウナギってタフなんだ、と改めて思いました。見習いたいですね。
さて、京都大学の主催で、サステナビリティや生物多様性に関する公開講座が開催されるのでご案内します。11月14日を第1回とし、全部で4回行われます。
名称: 令和7年度 京都大学生存圏研究所 公開講座
「クオリティ・オブ・ライフとサステナビリティ―」
日時: 2025年11月14日、12月5日、2026年1月9日、2月6日(全4回)17:30~18:30
会場: オンライン
主催: 京都大学生存圏研究所
参加費: 無料
主な内容:下記HPより抜粋
【第1回 11/14 廃カニ殻を有効活用したナノキチンの多彩なヘルスケア効果とその実用化の取り組み】
伊福 伸介 (生存圏研究所 教授)
カニ殻の主成分のキチンは豊富な未利用資源です。廃カニ殻の有効利用のため、新素材「ナノキチン」を開発しました。食べて良し、肌に塗って良し、植物に与えて良し。ベンチャーを起業して多様な機能を活用した実用化を達成できました。
【第2回 12/5 サステナビリティに貢献するマイクロ波加熱】
三谷 友彦 (生存圏研究所 准教授)
マイクロ波加熱は、電子レンジとして日常で広く利用されていますが、最近では環境負荷の低減に繋がるエネルギー源としても注目されています。マイクロ波加熱がなぜサステナビリティと繋がるのか?マイクロ波加熱の原理や利用方法を通じて紹介します。
【第3回 1/9 生物多様性とわたしたちの暮らし】
松葉 史紗子 (生存圏研究所 特定講師)
耳にする機会が少しずつ増えてきた「生物多様性」という言葉。生物多様性と聞いて思い浮かべるものは何でしょうか。本講演では、身近なつながりを手掛かりに生物多様性を紐解きながら、変わりゆく生物多様性とわたしたちの暮らしの未来を考えます。
【第4回 2/6 木材成分由来の化学製品とサステナビリティ】
岸本 崇生 (生存圏研究所 教授)
木材の主要成分は、セルロース、ヘミセルロース、リグニンという天然高分子化合物です。講演では木材の成分について概説し、それらの成分からつくられる食品添加物や工業原料など様々な化学製品について紹介します。
詳しくはこちらをご覧ください。