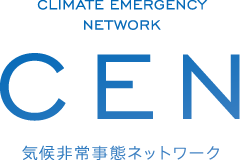日本の27の研究機関と200名超の研究者が取り組んでいる「S-18研究プロジェクト」があります。日本全国を対象にして、気候変動の影響や適応策・緩和策の評価、さらには予測も行う研究です。2018年に成立した「気候変動適応法」では5年ごとに全国的な影響評価を行って政府の適応計画を見直すことになっていますが、その土台となる重要な研究です。
この3月に過去5年間の研究をまとめた報告書が公表されました。
「日本の気候変動影響と適応策 -レジリエントで持続可能な社会に向けて-」
(このページの右コラムにある「S-18プロジェクト最終報告書」からダウンロードできます)
・産業分野(農業、水産業、畜産業、林業)
・自然生態系、水資源
・沿岸域や河川流域の自然災害
・生活・社会・経済
・地方自治体における取り組み
というように、さまざまな角度からの影響・適応評価がされています。
例えば水産業では、ワカメ養殖業、藻場生態系、底魚類(アワビ漁業、底びき網漁)について書かれています。ワカメの養殖については、三陸海域では生産量が増大する可能性があり、その一方で鳴門海域では成長が低下していることが指摘されています。地域によって影響やその程度が異なることが分かり、一つのテーマをほんの少し読んでみるだけでもなかなか
興味深いですよ。
さて、一般財団法人EDFジャパンの主催で気候変動と水産業に関するセミナーが開催されるのでご案内します。
名称: セミナー「気候変動のもとでの資源管理と評価の在り方を考える」
日時: 2025年5月15日(木)14:00~16:30
会場: TKP新橋カンファレンスセンターHall(千代田区)/オンライン
主催: 一般財団法人EDFジャパン (Environmental Defense Fund)
参加費: 無料
主な内容:下記HPより抜粋
【オープニング】
「挨拶」水産庁 資源管理部長 魚谷 敏紀 氏
「挨拶」調整中(ビデオメッセージ)
「趣旨説明」Fenjie Chen 氏(上級マネージャー/部門 代表 , 日本漁業海洋部門、
一般財団法人EDFジャパン )
【第1部:気候変動による、資源管理と評価の課題整理】
水産研究・教育機構研究戦略部 山崎 いづみ 研究主幹
(※表題調整中)
水産庁 資源管理推進室 赤塚 祐史朗 室長
「環境変動下における水産資源の持続的利用の確保に向けて」
UMINEKOサステナビリティ研究所(USI) 粂井 真 代表
「チャタムフィッシュ議論のまとめー日本周辺の海をめぐる危機と必要な対策」
宮城県庁水産業振興課 松浦 裕幸 課長
「宮城県沿岸域における海水温上昇が水産資源に及ぼす影響と対応策」
ディスカッション
「様々な課題解決に向けた優先順位とリソースの検討」
ファシリテーター:宮原 正典 氏 (よろず水産相談室afc.masa代表、元水産庁次長)
【第2部:米国商務省海洋大気庁海洋漁業局への出張ミッション報告】
水産庁資源管理推進室 赤塚 祐史朗 室長
「NOAA海洋漁業局との意見交換について」
水産庁資源管理推進室 加納 篤 課長補佐
「日本と米国西海岸の浮魚資源管理について」
水産研究・教育機構 水産資源研究所さけます部門千歳さけます事業所 江田 幸玄 氏
「日本と米国西海岸のさけ・ます類の増殖事業」
東京大学 阪井 裕太郎 准教授
「米国の資源管理から何を学ぶか」
質疑・ディスカッション
「アメリカの経験を参考に、日本の今後の進むべき方向、スピード感とタイムスケジュール」
ファシリテーター:宮原 正典 氏
【クロージング】
「閉会挨拶」白川 浩道 氏(一般財団法人EDFジャパン代表)
詳しくはこちらをご覧ください。