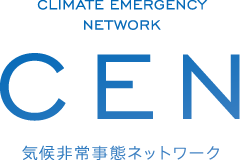ずっと前からあるのに、自分にとって新しい言葉にまた出くわしました。バイオリージョナリズム(bioregionalism)。日本語では「生命地域主義」とか「生態地域主義」として知られています。自分たちが住む地域の自然と人々との関わり合いを見直し、土地の特性を考慮して自然の生態系を回復・維持しながら持続可能な循環型社会を作っていくこと。そして地域と調和した産業や技術を創り出していくことです。
1970年代にアメリカの作家・エコロジスト・環境活動家だったピーター・バーグ(Peter Berg)が提唱したそうです。は、半世紀も前に提唱されていたのに知らなかったという…。穴があったら入りたいです。
彼が1973年に設立したプラネット・ドラム(Planet Drum)のサイトに”バイオリージョナリズム:イントロダクション”(2002年)という記事があります。Google翻訳を使うとありがたいことにページを丸ごと翻訳できるので、一読してみると参考になると思います。味のあるイラストがなんともいい感じです。
Planet Drum:Bioregionalism: An Introduction(2002)
さて、青山学院大学の主催でバイオリージョナリズムや環境学に関するシンポジウムが開催されるのでご案内します。
名称: 「AGU環境学シンポジウム」 ~バイオリージョナリズム(生命地域主義)を手がかりに水、環境と開発を考える:環境をめぐる人文科学・社会科学・自然科学の対話~
日時: 2025年7月12日(土)13:00~17:00
会場: 青山学院大学/オンライン
主催: AGU Environmental Studies Polyhedra(AGU環境学ポリヒードラ)
参加費: 無料
主な内容:下記HPより抜粋
【開会挨拶】
内田 達也(青山学院大学副学長、国際政治経済学部 国際経済学科教授)
【基調講演】
リチャード・エヴァノフ Richard Evanoff
(青山学院大学名誉教授〈元国際政治経済学部 国際コミュニケーション学科教授〉)
「Bioregionalism and Global Ethics(バイオリージョナリズムとグローバル倫理)]
(言語:英語)
【セッション1:〈地域〉における水】(言語:日本語)
・鳥越けい子(青山学院大学名誉教授〈元総合文化政策学部教授〉)
「音風景で辿る土地の記憶と感性」
・結城正美(青山学院大学 文学部 英米文学科教授)
「水のネイチャーライティングとBlue Humanities」
・三條和博(青山学院大学 経済学部教授)
「地域環境要因としての水」
・小松靖彦(青山学院大学 文学部 日本文学科教授)
「古代都市・平城京の水環境」
【セッション2:〈地域〉の視点からの環境と開発再考】(言語:日本語)
・堀江正伸(青山学院大学 地球社会共生学部教授)
「取り残された地域にとってのSDGs、グローバルバリューチェーン」
・島村靖治(青山学院大学 国際政治経済学部 国際経済学科教授)
「国際協力事業評価の再考―給水案件を中心に」
・石河泰明(青山学院大学 理工学部 電気電子工学科教授)
「太陽光発電の最新技術と廃棄問題への取り組み」
・南部和香(青山学院大学 社会情報学部教授)
「資源はめぐる、地域はつながる―都市鉱山から広がる地域資源循環の可能性」
【ディスカッション】
【閉会挨拶】
黄晋二(青山学院大学 理工学部長、理工学部 電気電子工学科教授)
詳しくはこちらをご覧ください。