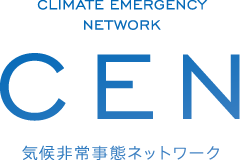アンゴラで降った雨が、数ヶ月かけて1,600km以上を旅して、内陸に広がる低地に辿り着き、やがて6,000~15,000平方kmというように季節に応じて広さが大きく変化する湿地を形成します。ボツワナの世界遺産、オカバンゴ・デルタです。この川は海には繋がっていないので、ほとんどの水はこの低地で蒸発していきます。
(オカバンゴ・デルタを理解する 2025年6月4日)
この湿地には15万もの島々があると言われています。乾燥した大地に水が流れ込んで湿地に姿を変えてもその島は水没ぜず、木々が生え、動物たちの休息の場になり、鳥たちが営巣する場所にもなり、オカバンゴの生態系を支えています。これらの島々はもとを辿ると、なんとシロアリが作ったアリ塚から始まっているのだそうです。この広大な湿地も、シロアリあってこその豊かな生態系なんだな…、と思うと、とても不思議です。
さて、WWFジャパンの主催で渡り鳥と湿地についてのウェビナーが開催されるのでご案内します。
名称: 生物多様性スクール2025 第1回 「渡り鳥の危機~湿地の重要性とは?」
日時: 2025年8月22日(金)18:00~19:30
会場: オンライン
主催: WWFジャパン
参加費: 無料
主な内容:下記HPより抜粋
食料や繁殖地を求めて、地球上で果てしない距離を移動する動物たちの多くが絶滅の危機にさらされており、特に渡り鳥の状況は深刻です。湿地や森林といった生息地の破壊や分断、気候変動の影響などがその原因です。その中でも渡り鳥にとって重要な生息地である干潟などの湿地は、開発や埋め立て、さらに気候変動の影響によって世界中で急速に減少しており、日本では1999年までの過去100年間で約6割以上の湿地が消失したとも言われています。
WWFジャパンは、1990年代から干潟などの湿地、渡り鳥を守る活動を数多く展開し、現在もモンゴルでのマナヅルの生息地保全や、大阪・関西万博が開催されている夢洲をめぐる湿地保全の活動等を行なっています。生物多様性保全や気候変動対策の鍵となる湿地の重要性、その象徴種である渡り鳥を守る活動について、WWFジャパン海洋水産グループの前川聡と淡水グループの羽尾芽生とともに考えます。
・イントロダクション
・井田氏からのテーマ解説
・WWF天野と井田氏の対話形式で今回のテーマを深掘り
・質疑応答
登壇者:
・WWFジャパン 自然保護室 海洋水産グループ 前川聡
・WWFジャパン 自然保護室 淡水グループ 羽尾芽生
・WWFジャパン理事、共同通信編集委員 井田徹治氏(モデレータ)
詳しくはこちらをご覧ください。