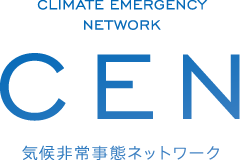南太平洋には旧イギリス領だった小さな島しょ国がいくつもあります。それらの地域が独立に向かっていた最中の1968年、将来を担う人材を育成するために各地域の政府が協力し、フィジーの首都スバに本部を置く南太平洋大学(University of the South Pacific)が設立されました。
複数の国が共同で設立した大学は世界でも例が少ないそうです。現在この大学の運営に参加しているのは12カ国。クック諸島、フィジー、キリバス、マーシャル諸島、ナウル、ニウエ、サモア、ソロモン諸島、トケラウ、トンガ、ツバル、バヌアツで、それぞれの国にキャンパスがあります。
2019年に、8つの太平洋島しょ国から来た南太平洋大学法学部の学生27人が教室に集まり、ある運動を始めることを決意しました。気候変動と人権問題を国際司法裁判所(ICJ)に持ちかけるように、太平洋諸島フォーラム(PIF)の指導者たちを説得するという運動です。「気候変動と闘う太平洋島嶼国の学生たち(Pacific Island Students Fighting Climate Change, PISFCC)」のはじまりです。
Pacific Island Students Fighting Climate Change
https://www.pisfcc.org/team
ICJには、国家間の紛争を解決する役割の他に、国連の諸機関の求めに応じて法律問題について勧告的な意見を述べるという役割があります。気候変動に関する問題を法律的側面から解決していく一つのステップとして「ICJにこの仕事をしてもらおうよ」というわけです。さすが、法学部の学生ならではの着目点ですね。
27人の草の根運動から始まり、やがて太平洋全域で100人以上のメンバーがそれぞれの国の政府に働きかけていきました。この活動は大きなうねりを起こしていきます。2022年8月に太平洋諸島フォーラムは第51回首脳会議を開催した際に、「気候変動と人権に関する国家の義務についての勧告的意見をICJに要請する」ことをフォーラムの加盟国全会一致で支持しました。
地域の足場を固めたら、次の舞台は国連総会が行われるニューヨークです。PISFCCが慈善団体、市民団体、学者などの支援を得るために活動を進める一方で、バヌアツ政府は国連総会決議案について中核的な国々と交渉を主導しました。
こうした活動が実って、2023年3月29日の国連総会で、ICJに勧告的意見を求める決議が全会一致で採択されました。
その後、各国・国際機関から陳述書や書面コメントが提出され、2024年12月にはICJの所在地オランダのハーグで口頭審理が行われました。96カ国の政府と11の国際団体が法廷で陳述を行い、PISFCCの若者たちも審理の初日と最終日に気候変動の危機に直面する太平洋地域の声を届けました。
そして2025年7月23日、ついにICJの勧告的意見が発表されます。今年3月にICJ所長に就任した岩澤雄司裁判所長が、
「国家には温室効果ガス(GHG)の排出から環境を守る義務があり、この義務を履行するために相当の注意を払うと共に、協力して行動する義務がある」
「もし国家がこれらの義務に違反した場合、法的責任を負い、不法行為の中止、再発防止の保証、および状況によっては全面的な補償を求められる可能性がある」
といった意見を読み上げました。
この勧告的意見に直接的な法的拘束力はないものの、今後の気候変動に関連する訴訟や対策などに影響を与える可能性は小さくなさそうです。
太平洋の島嶼国は気候変動による海面上昇、高潮、サイクロン、干ばつなどに直面しています。荒ぶる海の片隅に集まった27人の学生たちが始めた挑戦が世界を動かしました。歴史というのは人間が作るものなんだな、と改めて思いますね。
さて、環境NGO・NPO・市民団体の全国ネットワークである「グリーン連合」の主催で、国際司法裁判所の意見に関連したウェビナーが開催されるのでご案内します。
名称: こんなに温暖化が進んでしまって、この先どうしたらいいの?
~国際司法裁判所の意見を手がかりに次の行動を考える~
日時: 2025年10月6日(月)14:00~15:30
会場: オンライン
主催: グリーン連合
参加費: 無料
主な内容:下記HPより抜粋
国際司法裁判所(ICJ)は2025年7月23日に、気候変動対策について全ての国家に法的義務があるとする勧告的意見を発表しました。この勧告は、すべての国が温室効果ガス排出抑制などの具体的な対策を講じる義務があり、違反すれば国際的な不法行為とみなされる可能性があると指摘しています。さらに、気候変動から人権を保護する義務があること、民間企業による排出を規制する義務が国家にあることも示されました。
この判断を手がかりに、今、私たちが、気候変動問題にどう対処していけばいいのか、
専門家の方からお話いただき、ディスカッションしたいと思います。
プログラム
1.講演 「国際司法裁判所の勧告的意見書から何が読み取れるのか」
講師 明日香壽川さん
2.質疑応答
詳しくはこちらをご覧ください。