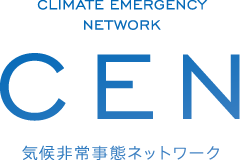「季節風」で知られる「モンスーン」という言葉の起源はアラビア語で”季節”を意味するmawsim(マウスィム、モウスィムン)にあると言われています。インドとアラビア半島の間に広がるアラビア海では毎年6月から9月にかけての暑い時期に大陸上空で上昇気流が発生するため、海から陸に向かって風が吹きます。冬になると海の上空の方が相対的に暖かくなるため、逆向きの風が陸から海に向かって吹きます。
帆船を使っていた時代には、定期的に風向きが変わるこのモンスーンを利用した海上貿易(季節風貿易)が広範囲に行われていました。1世紀半ばにエジプトを拠点にしていたギリシャ系商人によって書かれたとされる航海ガイドブック「エリュトラー海案内記」では、ローマ、ギリシャ、アラビア半島、アフリカ東海岸からインドにまで及ぶ貿易圏の港や航路、特産品などが紹介されています。
現在、モンスーンはアラビア海に限らず、東南アジア、オーストラリア、アメリカ大陸などの季節風やそれに伴って生じる雨期や大雨、嵐のことを指して使われています。中でも最大の”アジアモンスーン”は1万kmのスケールで発生し、日本の梅雨にもその影響は及んでいます。
この”モンスーン”を名に冠したモンスーン風力発電所(Monsoon Wind Power)が8月に稼働を始めました。ラオスでは初めての、そして東南アジアでは最大の陸上風力発電所です。場所はラオス南部セコン県。標高1,100mから1,700mの緩やかではあるものの複雑な地形の丘陵地帯に133機の風力タービンを設置しました。設置の様子が分かる動画があるのですが、ブレードを運ぶトレーラーを見たとき、「いやこれ、ひっくり返っちゃうんじゃないの?」なんて思ってしまいましたが、これでも行けるんですね~。
600メガワットの発電力を備え、今後25年間、国境を超えてベトナムに電力を供給していくそうです。電力需要がますます高まる東南アジアに、まさに新しい季節、新しい”モンスーン”がやって来たというわけですね。
さて、自然エネルギー財団の主催で洋上風力発電と漁業に関するフォーラムが秋田県で開催されるのでご案内します。(下記のリンク先のページから「漁業者のための洋上風力発電入門:地域の海の10年後を考える」という冊子をダウンロードできます。漁業関係者でない方にとっても興味深い内容です)
名称: 公開フォーラム 洋上風力と漁業の共生を考える 現場の声とこれからの展望
日時: 2025年10月17日(金)14:00~16:00
会場: 秋田市にぎわい交流館
主催: 自然エネルギー財団
参加費: 無料
主な内容:下記HPより抜粋
○ 講演1「洋上風力と漁業」
長谷 成人 東京水産振興会 理事 / 海洋水産技術協議会 代表・議長
○ 講演2「洋上風力と地域」
田中 圭 千葉県 商工労働部 カーボンニュートラル推進課 エネルギー産業振興室 副主幹
○ 講演3「漁業からの視点共有」
土合 和樹 フィッシャーマン・ジャパン・マーケティング 取締役 COO
○ パネルディスカッション「漁業と洋上風力の共生に向けた課題と展望」
・菊地 智英 秋田県漁業協同組合 専務
・竹内 彩乃 東邦大学 理学部 准教授
・村上 春二 UMITO Partners 代表取締役・創立者
・吉田 安貴 JERA Nex bp Japan合同会社 技術本部 建設計画・監理室
・田中 圭
[モデレーター]大林 ミカ 自然エネルギー財団 政策局長
詳しくはこちらをご覧ください。