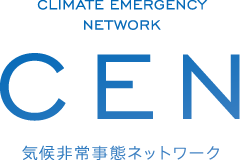ケニアの首都ナイロビの郊外に資源地図地域センター(RCMRD, Regional Centre for Mapping of Resources for Development)のオフィスがあります。1975年に国連アフリカ経済委員会(UNECA, United Nations Economic Commission for Africa)とアフリカ統一機構(OAU, Organization of African Unity)の支援によって設立された国際組織で、持続可能な開発のために必要な地理情報や関連技術を提供することを目的としています。農業や食糧安全保障、気候変動の影響、生態系の監視と管理、土地利用のマッピング、水資源管理、洪水災害の予測・調査、災害リスクの低減などに取り組んでいます。
創設時のメンバーは主に東アフリカの国々で、ケニア、ウガンダ、タンザニア、ソマリア、マラウィの5カ国でしたが、現在ではスーダン、エチオピア、マダガスカル、アンゴラ、ジンバブウェ、ナミビア、南アフリカなどを含む20カ国に広がっています。
PASSAGE: Strengthening Pastoral Livelihoods in the African Greater Horn through Effective Anticipatory Action
”アフリカの角”地域の牧畜民に対して旱魃リスクの早期警報と予測的行動に関するシステムを強化。
RCoE:Regional Centre of Excellence
科学技術イノベーションを活用し、生物多様性や森林、海洋に関する正確な情報を提供し、環境問題を解決しながら、地域住民にも有益な生態系サービスを支える。
GW4R:Groundwater for Resilience
”アフリカの角”地域における持続可能な地下水利用の推進。人材育成、情報提供、開発、管理などを行う。
などプロジェクトを実施しています。
10月29日、小型衛星の設計から運用まで行う日本のベンチャー企業アクセルスペースが、ガーナの宇宙科学技術研究所とこの資源地図地域センター(RCMRD)とも覚書を締結し、人工衛星の地球観測データを利用して社会課題の解決に向けて協力していくとの発表がありました。鉱山や森林のモニタリングを行うだけでなく、衛星の活用や宇宙機関の人材育成などを支援していきます。こうした協力が、やがてはアフリカの国々の気候変動対策にも役立っていくことを期待しています。
さて、日本自然保護協会と環境省の主催で里地調査に関するシンポジウムが開催されるのでご案内します。平成15年から日本の高山帯や森林、草原、里地、沿岸域、サンゴ礁など様々な生態系のモニタリングが全国1,000箇所での調査地(モニタリングサイト)で行われています。この成果などについてのシンポジウムです。
名称: モニタリングサイト1000里地調査 2025年度シンポジウム
「里地調査を通した次世代の自然の守り手育成~学校や学生との連携を事例に~」
日時: 2025年11月22日(土)13:30~16:00
会場: オンライン
主催: 日本自然保護協会、環境省生物多様性センター
参加費: 無料
主な内容:下記HPより抜粋
○ 開会挨拶
環境省 生物多様性センター長 常冨 豊
○ 話題提供
「モニタリングサイト1000とは?」
環境省 生物多様性センター 平松 新一
「モニタリングサイト1000里地調査の成果と課題」
日本自然保護協会 藤田 卓
○ 基調講演
「自然を知る・地域を知る~学校や学生と進める自然環境調査の意義~」
美幌博物館 鬼丸 和幸氏
○ 学校や学生と連携した調査サイトの事例紹介
1.「市民団体と大学部活が連携して調査」(神奈川県)
山田 健一氏(奈良川源流域を守る会)、守屋 大地氏(玉川大学生物自然研究部)
2.「公園管理に参加する教育プログラムとして活用」(東京都)
片山 敦氏(NPO法人 フュージョン長池)
3.「哺乳類調査で学校との連携を構築中」(神奈川県)
森 拓也氏(逗子市役所)、山浦 安曇氏(理科ハウス)
「多様な主体と連携した調査のためのポイント」
鬼丸 和幸氏 (美幌博物館)
○ 総括・クロージング
詳しくはこちらをご覧ください。