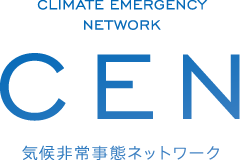江戸時代中期の浮世絵師、鳥山石燕(とりやま せきえん)が妖怪図鑑とも呼べる「図画百鬼夜行」を描きました。天狗や河童、かまいたちなどとともにカワウソ(獺)も描かれています。カワウソについては東アジアではさまざまな形で人を化かす伝承が伝わっていて、日本だけでも「美女に化けて、近寄ってきた男を食い殺す」「カワウソに取り憑かれると魂が抜かれる」「生首に化けて漁の網にかかり驚かす」など、なかなか重量級の恐ろしい伝説があちこちにあります。
賢い動物としても知られており、捕まえた魚を岸に並べる習性を持つ種もいて、その様子がまるで先祖への供物を並べて祭っているように見えることから、獺祭(だっさい)と呼ばれています。
このように人との繋がりが深く、明治時代までは日本中に生息していたカワウソも、毛皮や薬(肝臓が肺結核の薬に使われた)目的の乱獲や環境破壊によってその数は急減し、1979年の高知県での目撃を最後に日本ではその姿が見られなくなり、2012年には環境省が絶滅を宣言しました。ところが2017年2月、対馬でカワウソの姿が映像で捉えられました。実に38年ぶりに現れたことになります。
韓国から渡ってきたと考えられるこのカワウソたちは今も対馬にいるようで、これから日本に定着していけるかどうかが注目されています。妖怪としては恐ろしい力を持っているカワウソですが、河川の生態系では上位捕食者であり、食物連鎖のなかで汚染物質も蓄積されていくため、環境汚染に対しては脆弱だと言われています。カワウソが生きていける環境を維持・回復できるのか、生態系保護のひとつの指標になりますね。
さて、日本アジアカワウソ保全協会の主催で日本のカワウソに関する国際シンポジウムが開催されるのでご案内します。
名称: 国際シンポジウム「日本のカワウソのこれまでとこれから―海外の事例から考える」
日時: 2025年8月30日(土)、31日(日)13:00~16:30
会場: 長崎市立図書館(30日)/東京農業大学(31日)
主催: 日本アジアカワウソ保全協会
参加費: 無料
主な内容:下記HPより抜粋
本シンポジウムは、対馬で発見されたカワウソに関する国際シンポジウムとしては国内で初めての試みであり、国内外のカワウソ専門家が一堂に会する貴重な機会となります。
2017年、絶滅したとされていた対馬でカワウソの生息が確認されました。調査の結果、韓国から自然分散してきた可能性が高いことが分かり、現在までにオス2頭以上、メス2頭の個体の存在が確認されています。その後、7年経過した昨年にも糞が確認できたことから、対馬で繁殖しているか再度韓国から渡来したと考えられます。現在、日本でカワウソが定着、復活する可能性があるのは対馬だけです。
本シンポジウムは、対馬での生息状況、一度絶滅したカワウソを復活させたオランダの実例紹介、対馬のカワウソの元の個体群と考えられる韓国のカワウソの生息状況、対馬の磯焼けなどの現状などを紹介し、カワウソの復活に向けて議論する場を提供し、対馬の生態系、生物多様性の保全について考えるきっかけとなればと考えております。
「日本のカワウソの歴史と対馬の現状」
佐々木浩 本協会理事長、筑紫女学園大学
「オランダにおけるユーラシアカワウソ復活・再導入」
アディ・ディ・ジョン氏 カワウソステーション財団
「韓国におけるユーラシアカワウソの生息状況」
ハン・ソンヨン氏 韓国カワウソセンター所長
「対馬の磯焼けなどの海の現状」
釜坂 綾氏 元・対馬市島おこし協働隊 海の森再生支援担当
詳しくはこちらをご覧ください。