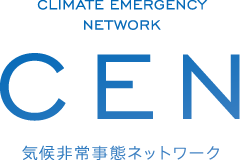南極の氷床融解が進んでいる、という話は時折聞きますが、実はそのほとんどが南極の西側沿岸部のことであり、観測機器が少ないことから東側の内陸域での気候の変化についてはあまり分かっていなかったそうです。
今年7月に公開された名古屋大学、国立極地研究所、北見工業大学などの研究成果によると、南インド洋の温度上昇の影響が南極の内陸域まで及んでいて、世界平均よりも速い速度で平均気温が上昇していることが分かりました。
南極内陸域で世界平均より早い気温上昇を初観測
~南インド洋の温暖化が南極の氷を溶かす~(2025年8月7日、国立極地研究所)
過去30年間(1993年-2022年)の三つの観測地点の気温データから、3地点とも10年ごとに約0.45-0.72℃上昇していることが分かりました。気温上昇の世界平均が10年ごとに0.2-0.25℃とされているので、倍以上のペースで上昇していることになります。
この研究は、南極の東側の内陸域の気候変動を初めて明らかにしたのですが、”初めて”分かったということで、重要な点があります。なにしろ初めて分かったことですから、この「インド洋の温暖化に伴う南極内陸域の温暖化」というプロセスは、現在の気候モデルには組み込まれていません。それはつまり、この地域のこれまでの温暖化予測は現実を過小評価してきたかもしれない、ということになります。
こういう話は知れば知るほど気が重たくなってしまいますが、知らないままでいるわけにも行きませんよね…。今後も観測と研究が進んで、私たちが知っておくべきことがさらに明らかになっていくことを期待します。
さて、九州大学の主催で脱炭素型循環経済システムに関するシンポジウムが開催されるのでご案内します。
名称: 「品質」と「デザイン」が家庭系廃プラ・リサイクルの明日をつくる
(環境省「脱炭素型循環経済システム構築促進事業」プロジェクト報告シンポジウム)
日時: 2025年9月3日(水)13:30~16:30
会場: 九州大学/オンライン
主催: 九州大学
参加費: 無料
主な内容:下記HPより抜粋
〇 開会挨拶
全体概要:地域で取り組む材料プラスチックリサイクルの成果と課題
・大木町を中心とした取り組みの経緯
・地域住民にとってのプラスチックリサイクルのシステム整備と見える化
近藤 加代子(九州大学芸術工学部 教授)
〇 報告1「リサイクル困難材の材料改質検討」
加賀 正剛(いその株式会社製造本部 副本部長)
〇 報告2「リサイクル困難材の出口商品の検討」
酒井 秀樹(岐阜プラスチック工業株式会社 執行役員・サスティナブル戦略室 室長)
〇 報告3「DNPの資源循環への取組み事例のご紹介」
佃 えり子(大日本印刷株式会社 Lifeデザイン事業部 第3ビジネスユニット開発本部 製品開発第2部 第1グループ 主幹技術員)
〇 報告4「プロダクトリサイクルデザインから、トランジションデザインへ」
尾方 義人(九州大学芸術工学部 教授)
〇 報告5「プラスチックの高品質リサイクルを対象としたライフサイクル環境評価」
松本 亨(北九州市立大学 環境技術研究所 教授・カーボンニュートラル推進部門長)
〇 報告6「企業の脱炭素効果及び製品デザインの脱炭素効果に関する評価」
早渕 百合子(九州大学洋上風力研究教育センター 教授)
〇 報告7「回収方式による製品プラスチック排出実態の違い」
鈴木 慎也(福岡大学工学部 教授)
〇 報告8「プラスチック・リサイクル・C Psの実証事業:SC と今後のリサイクル」
久保 直紀(プラスチック容器包装リサイクル推進協議会 理事・会長補佐)
〇 基調講演「容器包装リサイクルプラスチックの高度再生利用~潜在能力を活用する~」
八尾 滋(広島大学 客員教授、福岡大学 名誉教授)
〇 講評・プロジェクト評価
境 公雄(前大木町 町長)
〇 閉会挨拶
近藤 加代子
詳しくはこちらをご覧ください。