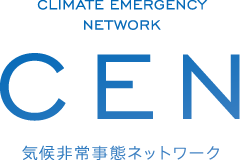温暖化が進行している現在、干ばつや塩害、農業に適した土地の減少など、世界の食糧生産の行く末が危ぶまれています。そんな状況を克服するために、高温に強い作物や、海水でも栽培できる作物を開発しているのが2019年に設立されたALORA社。
今年1月には、日中気温が40℃超、夜間気温が32℃超の環境下でも育つ稲を開発しました。対象群の稲と比較して2,555%の収量増加で、1ヘクタールあたりの推定終了が11トンになったそうです。
農林水産省のサイトによると、令和6年の日本の水田における10アールあたりの収量は540kgとされています。1ヘクタールは100アールなので、1ヘクタールの水田からの収量は5.4トンだと言えます。だとすると、このALORAの稲は、2倍の収量を達成していることになります。そのおいしさや品質については分かりませんが、収量だけを見ると驚異的ですよね。
また、塩分に耐性があって海水で育つ作物ができると、海に農場を作れるようになります。ALORAのサイトに想像図が描かれていますが、これが実用化されると、どんな乾燥地でも海があれば農業が可能になるし、塩害によって農業に適さなくなった土地でも農業ができるようになります。適応できそうなものとそうでないものはありますが、いずれにしても「農地」の概念がひっくり返りそうですね。
さて、筑波大学が中心になって設立された「ゲノム編集育種を考えるネットワーク」の主催で気候変動に適応したコメに関するセミナーが開催されるのでご案内します。
名称: セミナー「気候変動に克つ!育種技術が切り拓く次世代コメ品種開発の最前線」
日時: 2025年8月29日(金)15:00~17:00
会場: オンライン
主催: ゲノム編集育種を考えるネットワーク
参加費: 無料
主な内容:下記HPより抜粋
気候変動による高温・干ばつなどの環境ストレスは、水稲の安定生産に深刻な影響を及ぼしています。こうした状況に対し、育種の現場では、環境ストレスに強いコメ品種の開発が加速しています。
本セミナーでは、4名の講師をお迎えし、気候変動下でも安定して収量・品質を確保できる育種技術を適用した次世代コメ品種の開発、コメの生産の現状および将来像について幅広い視点で講演いただきます。
「高温耐性品種「にじのきらめき」の紹介」
長岡 一朗 氏(農研機構 中日本農業研究センター(上越研究拠点)水田利用研究領域 作物開発グループ)
「レジリエントな収穫、上昇する海面: ALORAの高温耐性および海洋栽培用品種で米の未来を拓く」
ルーク・ヤング 氏(ALORA Innovation Inc. CEO)
「これからの水稲経営の現場で求められる品種改良とは」
徳本 修一 氏(トゥリーアンドノーフ(株) 代表取締役)
「コメにおける新規(技術)事業 国内&海外」
有馬 暁澄 氏 (Beyond Next Ventures(株) パートナー)
【総合質疑・パネルディスカッション】
ファシリテーター
高橋 宏和 氏 (名古屋大学 大学院生命農学研究科 准教授)
津田 麻衣 氏(東洋大学 食環境科学部 准教授、ゲノム編集育種を考えるネットワーク)
詳しくはこちらをご覧ください。