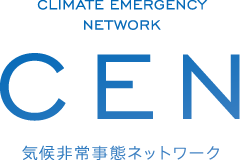月光。夜の闇をうっすらと照らす光。ちょっとロマンチックな響きがありますね。楽曲のタイトル、菩薩の名前、はたまた昔の夜間戦闘機の名前に使われていたりします。この月光もまた生態系にとって大切なのだということを改めて知りました。
5月27日に公表された研究で、世界の海が「暗くなっている」ことが分かりました。
Darkening of the Global Ocean (世界の海の暗化、Global Change Biology/ Volume 31, Issue 5, WILEY)
太陽光が届き、植物プランクトンが光合成を行える水の層「有光層」。一般的には海表面の光が1%になる水深までを指していて、外洋では50mから200mほどの範囲です。光合成や化学合成によって炭素を含む無機物から有機物が生産される、つまりバイオマスが生産されることを「基礎生産」と言いますが、有光層はこの基礎生産が行われる重要な層。まさに海洋生態系の基盤をつくる層ですね。
過去20年(2003年から2022年)の間に、世界の海洋の5分の1において光が届く深度が浅くなっている、つまり有光層が浅くなっていることが分かりました。世界の海の9%で、有光層が50m以上浅くなっています。200mの層の4分の1がなくなっている、ということになります。
月の光に合わせて生殖行動を行ったり回遊したりする生物もいます。例えばサンゴは満月の前後に産卵しますよね。その月光が届く範囲もまた、14%ほどの海域で10m以上浅くなっているそうです。ということは、サンゴの産卵や生息域にも影響を与える可能性も考えられます。
論文の最後はこんな言葉で締められています。
”成長、移動、捕食、コミュニケーション、繁殖、光合成に必要な十分な光がなければ、海洋生物は、十分に明るい表層水域がますます狭まるにつれて、垂直方向に移動せざるを得なくなり、資源をめぐる競争の激化と捕食リスクの増大に晒されることになる。海洋食物網、世界の漁業、炭素収支および栄養収支への影響は深刻となる可能性がある”と。
原因として温暖化によるプランクトンの増加や海洋循環パターンの変化の可能性も挙げられていますが、調査した期間が20年に限られているため、自然な変動を反映している可能性もあるとのこと。さらなる研究を待ちたいですね。
さて、株式会社バイウィルの主催でカーボンネットゼロに関するセミナーが開催されるのでご案内します。
名称: 「カーボンクライシスへの備え(2)」レポート解説セミナー
日時: 2025年8月8日(金)14:00~15:00
会場: オンライン
主催: 株式会社バイウィル
参加費: 無料
主な内容:下記HPより抜粋
2025年5月、バイウィル カーボンニュートラル総研は、『カーボンクライシスへの備え』第一弾を作成・発信しました。
2025年7月に発行した無料レポート「カーボンクライシスへの備え」第二弾では、企業の脱炭素の最前線を担う担当者に対して独自のアンケートを実施し、ネットゼロに向かう様々な企業で実際に脱炭素を担う人材が、こうした状況をどのように捉えているのか?そして、『カーボンクライシス』を回避し、ネットゼロを実現するための真の障壁が何なのか?ということについて、深堀りしています。
本セミナーでは、国内外の気候政策やGX-ETSの動向を踏まえ、独自アンケートに基づいた企業の現場におけるリアルな課題意識とその背後にある構造的な障壁を可視化するとともに、その障壁を乗り越えるためのヒントについて詳しく解説します。
講師
伊佐 陽介
取締役CSO 兼 カーボンニュートラル総研所長
詳しくはこちらをご覧ください。